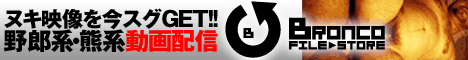作・出演(笑) 飛田流
二〇〇八年十二月三十一日、夜十一時過ぎ――。
日本中の多くの人々が仕事納めをして、穏やかな気持ちで新年を迎えようとしている中(そうでない人も今年は多いらしいけど……)、一人の無名のエロ小説書きはこの日も自分の部屋で半分壊れたパソコンと向かい合っていた。
どうも、僕です(笑)。
先日、無理にお休みを取らせていただいたこともあって、今年は年始に掛けて休みなくシナリオを書かせていただく予定だ。
もちろん今日も、朝から一歩も外に出ずに担当しているゲームのシナリオを書いていたわけだが……。
一人で。
「寒……ぅ」
殺風景な六畳一間の部屋の片隅にある、扇風機みたいな形のハロゲンヒーター一個では、寒々とした部屋を暖めるには少々の無理があるようだ。冷え切った両手の指先を毛羽立ったスウェットの太股の間に挟んで、とりあえずの暖を取る。
「ふぅ……」
僕は、腿に手を挟んだまま、椅子の背もたれに背中を預け、大きく伸びをした。
「今年も書いてばっかりの一年だったなぁ……」
この僕が、商業ゲームのシナリオを書くなんてなぁ……。
で、去年の大晦日は、LoveBに投稿する小説を書いてたんだっけ……。
「……はぁぁ」
自由業には盆も正月もない。仕事があろうがなかろうがなかろうが、ただただ作品を書くのみ。
「で、今年も結局『おひとりさま』脱出ならず、かぁ……」
ため息交じりに、この日何度目かの愚痴を口に出した時だった。
♪〜
パソコンデスクの傍らに置いていたケータイが、突然冷え冷えとした静寂を破った。
この軍歌調の着信メロディは……飛流大学の応援団団歌だ。
ケータイを開くと、画面にはむさ苦しいひげ面のおっさんの写真が映っていた。
いや、「おっさん」は失礼か。こいつは、男の僕が生み出した、大切な可愛い「息子」たちの一人、安岡大吾なのだから。
腿から手を抜いてケータイを取り上げた僕は、テンションの低い声で電話に出た。
「大吾、久しぶり。元気でしたか」
『げ、“元気でしたか”じゃないっ、飛田ちゃん!』
ケータイから大吾の野太く、野郎臭い声が響いた。大吾の口調はいつもこんな感じなのだが、なぜか怒気まで含んでいる。
『おいっ、俺と田上ちゃんの話はあれからどうなっとるんだっ!! ついに年を越してしまうだろうがっ!!』
「……っ」
鼓膜に突き刺さる胴間声に、一瞬耳がキーンとした。きっと大吾のことだから、キスをせんばかりにケータイに口を近づけて、唾を飛ばし怒鳴りちらしているのだろう。
「すまないけど大吾、もう少しだけ待っててくれませんか」
『駄目だっ、もう待てんっ!』
そっけなく返した僕の言葉が、燃えさかる大吾の激情にさらに油を注いでしまったようだ。
『これまでずーーーーーーっと、あの続きを待っとったんだぞっ! 一体俺はいつまで待っとればいいんだっ』
次々と浴びせられる大吾からの“尋問”に追いつめられた僕は、言葉に詰まる。
「そ、それはぁ……」
すると、それまでのトーンから一転して大吾の声が急に小さくなった。
『田上ちゃんと会えない日が何か月も続いて……、な……何度
せんずりで枕を濡らした夜が続いたことか……』
「……。大吾、落ち着いてよく聴いてくださいね」
スルーして、僕は続ける。
「大吾も知っての通り、僕は今、商業ゲームのシナリオを書いています。この作業を何よりも最優先しているので、大吾と勇一の話も後回しになっているんです」
『な……なんで俺たちの話のほうが先なのに、後回しにされにゃあならんのだっ』
「このゲームには、僕だけじゃなくていろんな人たちがスタッフとして関わっています。だから、僕だけの都合でシナリオを遅らせるわけにはいかないんです」
『そ……それはわからんでもないが……』
今度は大吾の声が詰まり気味になる。
『だとしても……ちょっとくらい、俺たちの話を書く時間だってあるだろが……』
「小説と違ってゲームというのはいろいろな展開があって、シナリオを書き上げるまでにかなり時間がかかるんですよ。――だから大吾には申し訳ないけど、まだ空き時間を作ることが……」
その後の言葉が見つからなくなった僕は、そのまま沈黙した。
『う、うむぅ……』とうめいたきり、大吾もまた黙り込んでしまった。
しばらくの気まずい沈黙が続いたのち。
『ひ、飛田ちゃんは……俺たちよりも、その……』
たどたどしく消え入りそうな声を、また大吾は口に出した。
「はい?」
『あ、葦沢っていう体育教師のヤツのほうを……ひ……ひいき、しとるんじゃ、ねえのか……』
「ひ……『ひいき』って」
なーんだ、大吾のやつ、結局のところ亘武に嫉妬してたのか。
三十越えたむさ苦しいおっさんが、他のゲームの、しかもBLのキャラに嫉妬するなんて……。
「……ははは、大吾ったら……」
僕は思わず笑ってしまった。だがそれが、大吾には違った意味に受け取られてしまったようだ。
『わ、笑ったなっ、いま飛田ちゃん笑ったなっ!! や……やっぱりっ、その体育教師のほうが、俺たちよりも……』
悔しげに絞り出された大吾の声から、ぎりぎりと歯噛みしている音まで聞こえてきそうだ。その剣幕に、僕はあわてて笑うのをやめ、フォローを入れる。
「そ、そんなことはないってば……。大吾も勇一も、そして、亘武も並木も、みんな同じくらい可愛くて大事な僕の“息子”たちですよ」
『いーやっ、その葦沢とやらや並木とやらのほうが俺たちよりもずーーーっと可愛いんだろうがっ』
「そんなすねないでよ……」
『もう……飛田ちゃんなんか知らんっ!』
プツッ。
ツーツーツー……。
「あ、キレた……」
ケータイを耳から離しても、まだ鼓膜がじんじんする。
今年の二月に『大吾、走る。』を発表してから、もうすぐ一年。大吾も勇一も、そして、読者の方も、当然ゲームが完成するまで、シリーズの続きを待ってくださっていると思っていた。
だけど、いくらなんでも、さすがに待たせ過ぎなのかもしれない。
「いや、でも……僕だって『あんなこと』になるとは思わなかったし……」
閉じたケータイを机の上に置き、僕は一人ごちる。
『大吾』は、もともとLoveBのために書き下ろした作品『一枚上手』が元になっていて、その後、同サイトと連動してこのシリーズは話が進むはずだった。少なくとも僕の頭の中では。
しかし、僕の『クロイヌ』が掲載された五月を最後に、このサイトは「時間が止まったまま」だ。(なぜ、よりによって僕の小説が「晒された」ままなのか……。苦笑)
そんな時にいただいた、この『体育教師極』のシナリオ執筆のお仕事は、無名のゲイ向けエロ小説書きにしか過ぎない僕にとって、またとない大きなチャンスだった。しかし、初めての商業作品、初めてのゲームシナリオ、これまでとは比較にならないぐらいの多くのユーザー……初めて尽くしのそれらに僕は戸惑いつつも、少し浮かれていたのかもしれない。
「どうすりゃいいんだろ……」
背もたれに上半身の全体重を乗っけて、また大きく伸びをする。
「わっかんないなぁ〜」
わかんないけど……とりあえず、僕が今しなければならないことは、ゲームのシナリオを一日も早く書き上げることだ。
僕はまた、椅子に座り直すと、キーボードの上に両手を置いた。だが――。
「……」
だめだ。
大吾のがなり声が耳について離れない。
「……はぁ」
そして、口からはため息しか出ない。
ゴーン……ゴーン……。
あ、除夜の鐘が遠くで聞こえる。もしかして、さっきから鳴っていたのかな。
パソコンの右隅の時計を見ると、新年、つまり午前〇時まで、あと五分だ。
「……あっ」
僕はあわててテーブルの上のリモコンを拾い上げ、テレビのスイッチをオンにした。別に見たい番組があるわけじゃないけど、せめて新年のカウントダウンぐらいはしたいからね。
『――さあ、いよいよ新年まで一分ですよっ。みなさん、カウントダウンの準備はよろしいですか?!』
テレビの中のスタジオで、増毛に成功した中堅のお笑いタレントが、ことさら大きな声で叫ぶ。すると、画面に「60」という文字が出て、59、58……とカウントダウンが始まった。
椅子の上で、僕が固唾をのんで画面を見つめた、その時。
ピンポーン
玄関でチャイムが鳴った。
「……」
何も聞こえなかったことにして、僕はテレビの画面を凝視した。
だが、次の瞬間。
ピンポーンピンポーンピンポーンピポピーンポーン
「って……誰っ!!」
誰だか知らないけどこんな時間に突然やって来て、しかもチャイムを連打するその無神経さに軽くキレた僕は、部屋を出るとダッシュで玄関に向かった。
「すいません、いまちょっと立て込んで……」
息を弾ませながら、急いで開けたドアの向こうに立っていたのは……。
「さっきは、すまんかったなぁ……」
ジャンパーと薄汚れたジーンズに褪せた藍色の前掛けをつけた、仕事着姿の大吾だった。足元の大きなスニーカーはかなり履き込んでいるのか、ぼろぼろに擦(す)り切れている。
「飛田ちゃんの事情も考えずに、俺、つい自分勝手なことばっかり言っちまって……本当に、すまん」
相変わらず無精ひげを生やした大吾は神妙な面持ちで頭を下げると、後頭部に手を置いてぼさぼさの髪をがりがりと掻いた。
「売り物(もん)ですまんが、ささやかながらこれで一緒に新年を迎えんか」
四角く大きな顔に、照れくさそうな笑みを浮かべる大吾の右手には、年始用ののしで包まれた一升瓶がぶら下がっている。
「……ぅぅ……」
しかし、一秒ずつ減っていくカウントダウンの数字が頭の中でちらついている僕には、これ以上大吾の話を聴いている余裕はない。
「そ、そんなことどうでもいいからっ!」
しびれを切らした僕は、酒瓶を差し出そうとした大吾の大きな手を強く引っ張った。
「おっ、ぉぉ……っ、どうしたんだっ、飛田ちゃん!」
身長一九〇センチはある体躯をよろめかせ、驚いた表情を見せた大吾に、僕は早口でまくし立てた。
「し、新年まで、あと一分切ってるんですよっ、早くしないと、カウントダウンに間に合わない!」
「カウントダウン、って……おぁっ、ちょちょ、ちょっと待て、おいっ!」
強引に大吾の手を引いて中に引き入れると、僕はまた全速力で部屋に戻った。スニーカーを脱いだ大吾も、どたどたと大きな足音を立てて僕の後を追う。
息を切らしながら僕は全速力で廊下を走る。そして、自分の部屋に転がり込んだ僕の耳には――。
『というわけで、二〇〇九年、明けましておめでとうございまーす』
高らかな新年のあいさつと、沸き返るスタジオの歓声が無情にも届いた。
「う、わぁぁぁ……」
年に一度の記念すべき瞬間を見逃した……。
取り返しのつかない事態に、脱力した僕の体はへなへなと床に崩れ落ちる。
「ど、どうしたんだぁ、飛田ちゃん」
数秒遅れて部屋に入ってきた大吾は、呆然と座り込んでいる僕を見下ろしながら、まったく訳が分からないという表情で、ただ首をひねっていた。
「も、もしかして、飛田ちゃん……」
一升瓶をどんと床に置いた大吾は僕の隣にしゃがみ込むと、ぶっとい腕を僕の肩に回した。
「そんなに新年のカウントダウンを楽しみにしとったのか……」
いまさらそんなすまなそうな声を出されても遅いんだよぅ……。
「もう……知らない……っ」
僕は床にうつむいたまま、泣きそうな声を上げた。
一年の初っぱなからこれじゃあ、今年もどうなることやら……。
「……」
しばらく黙ったまま、僕の肩を抱いていた大吾は、
「ったく……世話の焼ける『父ちゃん』だなぁ」
がしがしと僕の頭を大きな手でかいぐると、やおら立ち上がった。
完全に気持ちが落ちた僕には、顔を上げる気力も残っていない。僕は大吾から顔をそむけて、ただうなだれていた。
(……あれ)
すると、僕の耳になにやら奇妙な音が入ってきた。
服のすれる音、ベルトを外す音、ジッパーの開く音……。これは、まさか……。
(……も、もしかして……っ)
跳ね上がるようにして大吾を見ると、なんと大吾は、上半身の服は全部脱ぎ捨て、下半身はジーンズを今まさに脱ぎ始めようとしているところだった。一枚ずつ大吾が服を脱ぎ捨てるたびに、汗のにおいと雄臭い体臭が辺りに漂う。
「だ、だ、だだだだだ、大吾っ、何をいきなり……っ」
思いも掛けなかった大吾の行動にただあわてふためく僕に、大吾はむさ苦しい笑みをにっと浮かべた。
「俺がカウントダウンよりももっといーいこと、今からしてやっぜぇ」
にやにやと笑いながら大吾はジーンズも脱ぎ捨てると、ついに白ブリーフ一丁になった。
「い、いや、あの……なにも、そこまで……」
目の前に露になった、大吾の濃い体毛で覆われたがっしりとした筋肉、ちょっと緩んだ腹、少々黄ばんだブリーフの膨らみ。
あまりにも突然の展開に、僕は戸惑うばかりだった。
そんな僕の顔を見て大吾はまたにやりと笑うと、右手の人差し指で意味ありげにブリーフを指した。
「どうだぁ飛田ちゃん、ここの『中味』も見てみてえか」
「は……はぃぃ……」
本来は寒いはずのこの部屋で、耳まで真っ赤になった僕はこくこくとうなずく。
「よーし」とブリーフの縁(ふち)に両手の親指を掛け、大吾はおっさん臭い助平な笑みを浮かべた。
「まずは新年最初の『ご開帳』だぁ。ほーれ、よーく見てろよぉ……っ、と」
大吾が一気にそれを膝までずり下ろすと、
「……っ」
密集した体毛に包まれた、半剥けで赤銅色の巨砲が、ぶるん、と勢いよく飛び出した。大吾の股間でずろんとふてぶてしく垂れ下がるチンポは、まだ膨張の兆しさえ見せていないにもかかわらずその巨大さゆえに、ある種の威圧的な存在感さえ醸し出していた。
その最後のブリーフも脱ぎ捨てて、完全に裸になった大吾は、毛深い手でぼりぼりと股ぐらを掻くと、不敵な笑みを浮かべた。
「んじゃあ、そろそろ始めるとすっかぁ」
僕の心臓は破裂しそうなほど高鳴っていた。
「あ、あの……でも……いいの、かな……」
汗で滲んだ僕の目には大吾の毛深い巨躯(と、股間で垂れ下がっている巨大なもの)しか入らず、脳みそまでゆだり切った頭からは勇一の存在は完全に消え去っていた。
「まあ……大吾が、どうしても、って言うなら……」
仕方ないよね、とおずおずと立ち上がろうとした僕に、
「ああ、飛田ちゃんはそこで座って見ててくれ」
大吾は、平然とした口調で告げた。
「あ……え?」
中腰で固まり口を半分開けたままの僕を放置して、大吾はまっすぐ前を見据えると、
「んむぅ……ふぅぅぅー……」
大きな鼻の穴をさらに目一杯おっ広げて深く息を吸い、むさ苦しい無精ひげに覆われた分厚い唇をすぼめて長く息を吐いた。
続けて、大吾はすっと両手を真上に掲げた。両脇の下から現れたもっさりとした脇毛に、一瞬僕は目を奪われる。
それまでにやついていた大吾の顔が、急にきりりと引き締まった次の瞬間。
「フレー、フレー、ひ、だ、りゅうぅぅぅーーーっ!!」
突然大吾は、腹の底から部屋中に響き渡る声を張り上げた。
「……!! 大吾……」
ぶっとい手足を振り回し、部屋の真ん中で大吾は応援の演武を始めた。全裸ではあるけれど、単なる裸踊りのような滑稽さは微塵(みじん)もない。両の握り拳を力強く交互に正面に突き出す剛健な演武に、僕はただ見とれていた。
「押忍! 押忍! うーーーーっす!!」
空手に似た演武の型をひとつひとつ決めるたびに、大吾の毛深い体には汗が滲んでいき、半剥けのチンポもぶらんぶらんと股間で大きく揺れる。
寒々しい部屋の中で、真剣な顔でひたすら演武を続ける大吾の体からは、湯気と汗の匂いがうっすらと立ち上っていた。
そして、演武を続けながら、大吾は調子っ外れの声で「あの歌」をがなり始めた。
正義に集う若人よ
希望の空に茜燃ゆ
母校の名誉守り抜き
ここで尽くすぞ我がベスト
いざやその名を轟かさん
音程もめちゃくちゃで、はっきり言って音痴ではあるけれど。
その凛々しい姿は、僕の目には、学ランを着た十数年前の大吾の姿とオーバーラップした。
団歌を歌い終え、顔を真っ赤にした大吾は、また両手を振り上げた。
「フレー、フレー、たいいくきょぉぉぉしぃーーーっ!!」
そして、直立不動の姿勢に戻ると、「押忍!!」と両腕を毛深い胸の前で交差させ、深々と頭を下げた。
僕は、最初から最後までその熱演を呆然と眺めていた。
演武を終えた大吾は、汗が浮いていっそうむさ苦しくなったひげ面に、またいつもの人懐こい笑みを浮かべた。
「どうだ? 少しは元気出たかっ」
「だい、ご……」
胸の奥からこみ上げる熱い気持ちが、僕の声をまた少し震わせた。
感動醒めやらぬまま、ふらふらと立ち上がった僕は、熊みたいに大きな大吾の体をぎゅっと正面から抱き締めた。
「あり、がとう……っ!」
「お、おい……飛田ちゃん」
大吾が戸惑うのも構わず、僕は、その毛深くがっしりと盛り上がった胸板に顔をうずめていた。じっとりと濡れた大吾の胸からは、汗と体臭の入り交じったにおいがする。
「う、うむぅ……」
大吾はかなり困ったような声を上げていたが、
「ったく……正月だからな……今日は特別だぞ」
やれやれ、といった口調でそうつぶやくと、僕の背中に丸太のような腕を回してポンポンと叩いた。
僕たちは、しばらく無言で互いの背中に手を回していた。
ほてった大吾の体は温かく、その熱は僕の体を通して心にまで伝わっていった。
「びっくりしたよぅ……いきなり大吾、服脱ぎだすもんだから、まさか……って」
「ちょっと前だったら『そうやって』飛田ちゃんを慰めてやったもしれんが……」
大吾は、そこでいったん言葉を区切ると、
「田上ちゃんと出会っちまった今では、もう誰かれかまわず『そんなこと』はせん」
野太い声できっぱりと言い切った。
「それに……俺たちの関係は、そんな薄っぺらいもんじゃねえだろ」
「大吾……」
僕の体を抱き締める大吾の手に、少し力がこもった。
「俺と飛田ちゃんは一心同体。田上ちゃんと飛田ちゃんも一心同体。とにもかくにも飛田ちゃんがこの先を書き進めてくれんことには、俺たちにはどうにもできんのだ」
「ああ……うん」
照れた僕の声が、途端に小さくなる。
「それはいつになるかは、まだわからないけど……ね」
「わかっとるわかっとる。――まあ、俺の希望としちゃあ、今度は『田上ちゃんを』この腕に抱き締めてえとこだかな」
「……あっ」
その時、作者的にかなりヤバい行為をしていることにやっと気付いた僕は、あわてて大吾の体から離れた。
「……ごめん」
「ガハハ……なんだ、もう終わりか?」
大吾はいたずらっぽい笑みを返す。
「まあ、今日は『おひとりさま』同士、朝まで飲み明かそうじゃ……ふぇ、ふぇ……」
あっ、と思う間もなく、大吾のでかい小鼻がびくびくと震え、
「ブェックション!!」
ものすごいくしゃみがもろに僕の顔を直撃した。
「…………。だーいーごーぉぉぉぉっ」
「あ……いや、すまんすまん……」
大吾は決まり悪げな顔で、鼻の下を二、三度指でこすり、
「大学時代の寒稽古の時にゃマッパでも楽勝だったんだがなぁ」
大きな体をぶるりと震わせて軽く鼻をすすり上げると、床に脱ぎ散らかした服にいそいそと手を伸ばした。
――それから数時間後。
窓の外はそろそろ白み始めていた。
『感謝の裸踊り』の時と同様、手土産のはずの日本酒をほとんど自分で飲み尽くした大吾は、またもや床の上で大の字になると、盛大にいびきを掻いていた。そのむさ苦しくも愛らしい、無精ひげに覆われたおっさん臭い顔は、深酒のせいかだらしなく緩んでいる。
ちなみに、今回は二人ともちゃんと服を着ている(笑)。
「……ん?」
まだ少し酔いが残っている僕の目の端に、ちかちかと瞬く小さな青い光が映った。
その光が放たれているのは、パソコンデスクの上に置きっ放しだったケータイだった。青い光の点滅は、メール着信を知らせる合図だ。
僕は立ち上がって、デスクの上からケータイを取り上げた。
「……誰だろ」
開いて中を確認すると、二通、新着メールが届いていた。
その差出人は……。
「勇一……?」
そう、それは両方とも、田上勇一からのメールだった。 さっきから大吾が何度も「田上ちゃん田上ちゃん」と口にしている、当の本人である。
『謹賀新年』
明けましておめでとうございます。田上です。
もし、飛田さんのご都合がよろしければ、初詣のついでにお宅に立ち寄りたいのですが、よろしいでしょうか。
そのわずか三分後、勇一から続けてメールが届いていた。
『失礼いたしました』
すみません。
やっぱりご迷惑ですよね。
変なメールを送ってしまって、申し訳ありませんでした。
「ああ……」
送信日時を見ると、昨日の晩、つまり去年、大吾と電話で話していた時間にこれらのメールは送られていた。
現在時刻は、午前五時ちょい過ぎ。
今から電話で連絡を取っても、もう勇一は自宅のアパートに帰って寝ているかもしれない。
とりあえず僕は、メールを返信することにした。
『Re:謹賀新年』
勇一、明けましておめでとう。飛田流です。
もし、まだ家に帰っていないのなら、僕の家に立ち寄ってくれませんか。
僕も、長く出番を待たせてしまっているお詫びをしたいので、よかったらぜひ来てください。
P.S.
大吾も来ています。勇一が来てくれると、大吾もきっと喜ぶと思います。
(もし、勇一が来るとしたら……なにか温かい飲み物でも用意してやろうか)
メールを送信してケータイをズボンのポケットに入れた僕は、大吾を起こさないように足音を忍ばせて廊下に出た。
(ん……待てよ)
ふと、あることを思い出し、台所に向かおうとした僕の足は、回れ右をして玄関に向かう。
そして。
「ああ……やっぱり」
玄関に来ると、案の定大吾のスニーカーが、両方とも擦り切れた靴底を上にして、脱ぎ散らかされていた。
苦笑を浮かべて僕は、大吾の巨体に見合った、その二十九センチはあろうかというビッグサイズのスニーカーを揃えて、並べ直した。
ピッ……ピピッ……ピッ……
「えっ……」
その時、かすかな電子音が、耳に届いた。
僕は動きを止めて、その音に神経を集中する。
ピピ……ピッ……
♪〜
これは……ケータイの操作音だ。それに気付いたと同時に、
「……うわっ」
ポケットの中のケータイが震えた。
反射的にケータイを取り出して、中を確認する。
『申し訳ありません』
せっかくのお誘いですが、もう自宅に戻りましたので、ご訪問はまたの機会にさせていただきたいと存じます。
お気遣いありがとうございます。
それでは。
それは、勇一からの三通目のメールだった。
「まさか……っ」
あわてて僕は大吾のぶかぶかのスニーカーを突っかけると、おぼつかない足元で玄関に駆け寄り、ドアを開けた。
明るい群青色の空からちらちらと粉雪が舞う中、赤いパーカーを着て、ニットの帽子・マフラーを付けた男が、僕に背を向けて立っていた。その手にはケータイが握られている。
「勇一……?」
僕の呼び掛けに、ぎくりとしたその男はパーカーのポケットにケータイを突っ込むように隠した。
「……」
ゆっくりと振り返ったその顔は、やはり勇一だった。
まるで悪事を見つけられたかのように、ひどく驚いて、わずかに脅えたような表情を浮かべた勇一はそのまま唇を固く結んだ。
僕と目を合わせないまま、すみません、と小さな声で詫びた彼の形の良い唇から白い息が漏れる。
「立ち寄るつもりはなかったんですけど……つい」
と、勇一は頭を下げ、「それじゃ……」と逃げ去るように背を向けようとした。
「ちょ、ちょっと待って! せっかく来てくれたんだから、部屋でもう少し話でも……」
しかし、勇一はどこか悲しそうな顔で、首を横に振る。
「僕がここで安岡さんと会ってしまったら、前回のラストとつながらなくなってしまいますし……。それに……」
しばらくためらっていた勇一は、顔を上げて、僕の目をじっと見つめた。
「僕は……信じてますから。もう一度、安岡さんと会えることを……」
その澄んだ、悲しげな目に、僕は一瞬息が詰まる。
そして勇一は僕に背を向けると、そのまま歩き始めた。
「あ、あの……勇一!」
だんだん小さくなる赤いパーカーの背中に、僕は叫んだ。
「もしかして、そのパーカー、『あの時』からずっと……」
だが、今度は勇一は後ろを振り返らずに、僕の視界から赤いパーカーは消えた。
朝日が少しずつ空を赤く焼き始めていた。
「勇一……」
後を追うことはできた。でも、勇一の性格からして、たとえ追いついて問いつめたとしても、それ以上のことを口にはしないだろう。
――そう、そのキャラクター設定を決めたのは、他ならぬ僕自身だ。
僕は家の中に入り、玄関のドアを閉めると、また自分の部屋に戻った。少し冷えた体に、つけっぱなしのハロゲンヒーターの熱が温かく感じた。
ぐっすりと床の上で寝込んだ大吾は、酒のにおいをぷんぷんさせながらまだ、いびきを掻いていた。
「田上ちゃん」がさっきまで玄関にいたことも知らずに。
大吾と勇一のこれからの運命は、作者の僕の手に委ねられている。できれば、大吾も、勇一も、幸せにしてやりたいと思う。
しかし、今はまだ、その続きを書くことができない。
「……大吾……勇一……」
申し訳ない気持ちが、僕の心にじわりと広がっていく。
「はぁ……」
またため息をついた僕は、待機状態のパソコンのマウスに手を置き、わずかに動かした。黒い画面が切り替わり、『体育教師極』の書き掛けのシナリオが現れる。
「とにかく……これを書かなくちゃ、なんにも終わらないし、なんにも始まらないよな……」
そうつぶやいて、椅子に座った僕は、またシナリオを書き始めた。
(もう少しだけ待っててね……大吾、勇一)
一日も早くこのシナリオを書き上げて、また、小説を書こう。勇一と大吾の、滑稽でどこか切ない物語を。
心の中で僕がそう決心した、その時。
「うむぅ……いざや、その名を……ぐ、ふぅぅ」
僕よりもずっと図体の大きい「息子」の、むさ苦しくも愛らしい寝顔を、朝日はまぶしく照らし出していた。
※二〇〇八年十二月三十一日にアップした、ブログミニコント(笑)より。
ミニコント大吾と、「勇一・大吾シリーズ」本編大吾とは(ほぼ)関係ありません。